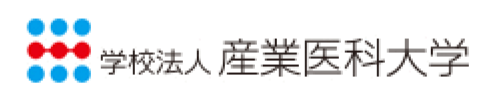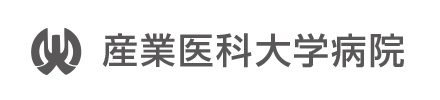教授あいさつ
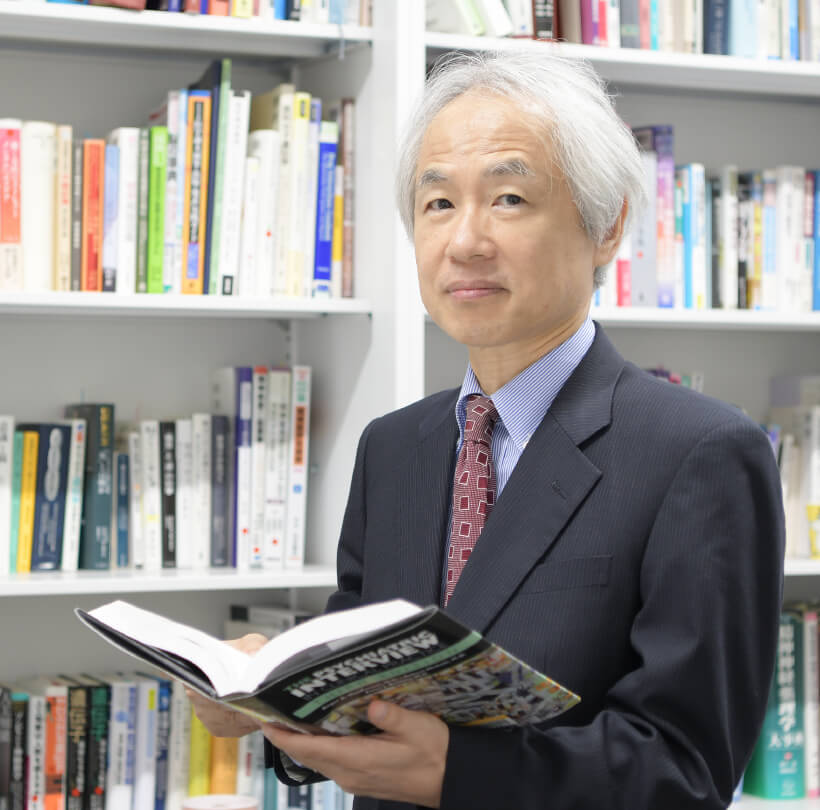
Reiji Yoshimura
教授 吉村 玲児
「わからないもの」とともに歩む勇気を
皆さん、精神医学の世界へようこそ。
私は大分医科大学を卒業し、産業医科大学神経精神科で約40年にわたり臨床に携わってきました。この間、精神科医療は劇的に進化を遂げました。かつて主流だった、臨床経験や直感をもとに診断や治療を行うスタイルは、いまや経験バイアスとして警戒され、DSMやICDといった操作的診断基準に基づく標準化医療が常識となりました。構造化面接の技術も進み、AIツールを使えば、世界中の最新の知見にも瞬時にアクセスできる時代です。たしかに、私たちは以前よりも「賢く」「正確に」なったように見えます。しかし、その便利さの影で、「自分で考え続ける力」や「わからないものに向き合い続ける勇気」を手放してしまってはいないでしょうか。
マニュアルに沿って診断し、ガイドライン通りに治療を行う。それだけで医療は成り立つのでしょうか。もちろん、標準化医療は医療の質を平準化し、安全性を高めるうえで不可欠です。しかし、精神医学の本質は、マニュアルでは捉えきれない「個」と向き合う営みにあります。理解できた、と思った瞬間に、患者さんはその枠を軽々と飛び越えていきます。精神医学とは、常に「あいまいで、わからない」ものに挑み続ける、ある意味で無謀な学問です。
私はいま、精神科医を志す若い皆さんにこそ、この「あいまいさ」や「わからなさ」とともに歩む覚悟を持ってほしいと願っています。わからないままでいることは、不安です。だからこそ、誰もが答えを急ぎたくなります。しかし、答えを求めるあまり、マニュアルや論文の「正解」にすがるだけの医療に陥らないでください。ガイドラインはあくまで「ヒント」に過ぎず、そこから本当に意味のある医療を紡ぐのは、あなた自身の思考と想像力です。
精神医学は、人間という存在を「想像しようとする」旅です。たとえ最初は的外れでも、少しずつでもその人に近づこうとする。そこに謙虚さがあり、人間らしさが宿ります。私は「他者を理解する」という言葉に、どこか傲慢さを感じてきました。完全に理解することなど、誰にもできないからです。しかし、想像することはできます。想像し続ける限り、私たちは患者さんの苦悩や希望に、少しでも寄り添うことができるのです。
精神科医とは、
「考え続け、問い続け、想像し続ける」存在です。
もし将来、テクノロジーが進歩して、脳の情報がすべて解読され、他人の苦悩を「本当に理解できる」時代が来たなら――それは医学にとっては大きな前進かもしれません。
しかし私は同時に、精神医学という営みの深さ、そして人間を想像しようとする美しさが、失われてしまうのではないかと、ひそかに危惧しています。
だからこそ、若き精神科医の皆さんへ。「わからないもの」を恐れず、「わからないもの」とともに歩んでください。その不安や迷いのなかにこそ、精神医学の豊かさと、人間への限りない敬意があるのです。